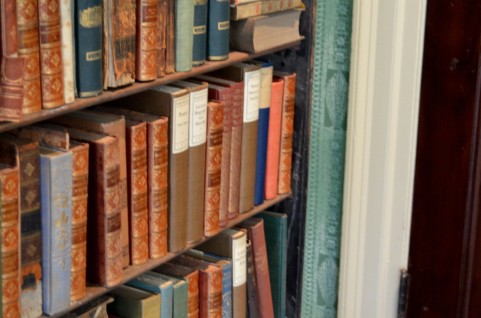本日アルバイト先で、勉強会と称した飲み会がありました。
そこで同じテーブルについたKさんから面白いお話を聴くことが出来ました。
良い道具=手が掛かる
Kさんは本業が木工職人で、副業として時間があるときにアルバイトをしているそうです。
本業の方では主に木工家具を作っていて、若い頃は修行のために全国各地の職人を訪ねて回ったそうです。
Kさんのお話によると、職人の道具へのこだわりは異常らしいです。
良い道具が高いのはもちろんなのですが、良い道具ほど自分に合うように調整をしてやらないと使い物にならないそうです。
良い道具=メンテナンス不要で楽ちん ってわけでもないんですね。
ホームセンターに売っているようなカンナはそれなりに調整が済んでいるので素人でも使いやすいのですが、プロが使うものとなると事情が異なるらしいです。
下手に高い道具を買ってしまうと、自分の手に終えずに「これは粗悪品だ」と一蹴して終わってしまうこともあるんだとか。
これって楽器も同じですね
良い楽器は買った時からある程度いい音はしますが、日々のメンテナンスを怠れば、あっというまに質が落ちてしまいます。
アコースティック楽器はとくにそうですね。マンドリンやクラシックギターは、良いものは表板が薄いので、冬の乾燥で割れてしまうこともあります。
割れるほどではなくとも、湿度温度によってコンディションがかなり左右されたりしますよね。
またどんなに良く整備された道具でも、生かすも殺すも使用者次第なところがあります。
「弘法筆を選ばず」という言葉がありますが、最高のパフォーマンスをしようと思ったら選んだ上で手を加えるまでしなければいけませんね。
(2015/11/6のリライト)