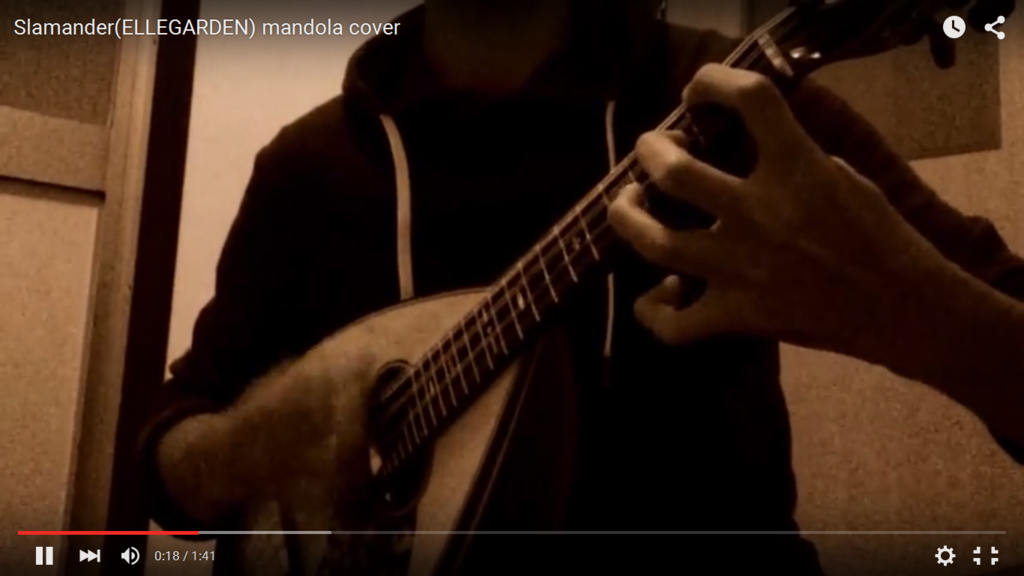エージングとは
「楽器を弾きこむ程よく鳴るようになる」とは、マンドリンに限らずよく言われる話。これには、2つの原因がある。
- 弾く人の演奏技術が向上する。
- 楽器が、構成する分子レベルで変化する。
1つめに関してはまあ当然っちゃ当然。長く弾いてれば誰でもある程度は上手く鳴らせるようになる。
2つめは、エージングと呼ばれる効果。
よく弾き込まれた楽器は、新品のそれと比べて豊かな響きが得られるという話。楽器奏者ならば誰でも聞いたことある話だと思う。
楽器だけでなくヘッドホンを語る上でも起こる話らしい。
「ヘッドホンのエージングで音が良くなるのは都市伝説だ」という意見もあるし、音が変わるという意見もある。
楽器のエージングも頻繁に取り沙汰される話だけど、調べてみてもいまいちピンと来ない。
「よくなった!」とは書いてあるが、あくまで主観的で、科学的に検証された客観的な情報が見当たらない。
エージングに効果があるとわかった所で、弾く以外の選択肢がないからだろうか。
しかし気になってしまったものは仕方がない。
そこで今回は、振動スピーカによって機械的にマンドリンのエージングを行い、エージング前後での周波数帯域(以下スペクトル)の変化を観察した。
実験方法
今回の実験には、G線(4絃)を用いる。(なんとなく。端っこの絃だから。)手で絃を弾くのは自由度が高すぎるため、以下の手法によって撥弦を行う。
- 紐を絃の片方に通し、目安となるフレットの端まで水平に引っ張る。
- ハサミで紐を切る。
これにより、同様に撥弦できているものとする(希望)。
この際の注意点として、撥弦の際に楽器が不用意に動かないよう、楽器ケースに入れたマンドリンの隙間にクロスを詰めて固定した。
また、共鳴、またはノイズを防ぐために他の弦だけでなくナットやブリッジの外側の絃にも振動止め(エリエール)を挟んだ。
撥弦位置から10cm離した位置にダイナミックマイク(BEHRINGER XM8500)を設置した。
音波の解析には、NCS SoftwareのWavePad FFT周波数解析ソフトを用いた。解析する位置は、発音直後を除いた最も音量が大きくなった部分である。発音直後はノイズが多く含まれるから。
エージング
振動スピーカー(デバイスネット ピタッとスピーカー)で、楽器を強制的に振動させる。
これを小一時間強制的に鳴らす。
うるさいから廊下でやった。それでもうるさいから蓋を閉じた。
以上の手法で、観測→エージング→観測と実験を行った。
結果 / 考察

上の図は、音量の変化の時間依存性を表したもの。
発音直後に最も音量が大きくなっているが、これはノイズがかなり含まれているため観測対象外とした。
うなりが発生しており、僕がチューニングが下手なのがバレた。
そして、発音直後を除いて音量が最大になる位置で、エージング前後のスペクトルを比較した。

左がエージング前で、右側がエージング後のスペクトルである。縦軸が音量で、横軸(対数表示)が周波数を表している。
一番左のピークが元の音であるG2(約195Hz)の音で、右に続くピークはその倍音。
音量の規格化は行っていないが、やり方がよくわからないし、だいたい同じぐらいの音量で鳴っているので、まぁよし。
3000Hz~6000Hzのあたりを比べると、エージング後ではこの辺りの成分が増加していることがわかる。およそG6(3136Hz)からF#7(5920Hz)なので、およそ1オクターブ分の幅の成分が良く鳴るようになった。
まとめ
弾きこむだけでなく、外部から振動を与えて直接ボディを鳴らすことでもエージングの恩恵は得られそう。
音のスペクトルの幅は狭いほどきらびやかで、太いほどやわらかい音になるので、自分の好みに合わせてエージングを行ってみるのもいいかもしれない。
今回は楽曲(同じ種類の楽器を用いた音)を用いてエージングを行ったが、ホワイトノイズやピンクノイズについても同様の効果が得られるのかどうかの検証も行いたい。